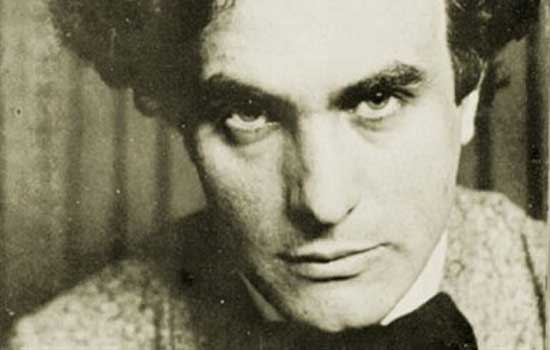こんばんは。
許しがたいサボリン加藤です。
さぼりすぎてブログのパスワード忘れるとこでした。
趣味はワインレッドのマニキュアを塗って、手の甲の静脈の緑とのコントラストを楽しむことです。好きな味は塩味です。そんなタワゴトはおいておいて、今日はちょっと寒いですね!9月の最初の寒い風が吹くときってなんか寂しいですよね。夏が終わりみたいで。ま、夏は大嫌いなんですけどね。
ちょっとブログを休んでいる間にいろいろありましたね!911の10周年や首相が交代したり中東ではまだまだ混乱が続いていますね。アメリカではだんだん大統領選にむけて共和党の候補者たちがうるさくなってきましたね。
個人的なニュースですが最近国連でインターンを始めました。以前よりも様々な世界情勢に触れる機会が増えたので、今回はタイトルのとおり、世界政府について書こうと思います。
世界政府というとどんなイメージですかね?
全世界を支配する政府で何か恐いイメージを持つ人が多いんじゃないかな?英語だとworld governmentとかglobal governmentっていいます。世界政府じゃなくてもっと良い訳があれば教えてください。 簡単にいうと、国際社会では国の上にそれらを支配するさらに上の機関とか政府といったものは存在しないですよね?世界政府はそいいう役割を担う物で、超国家的な存在として国際問題の解決に中立的立場で関与しようという考えなんですね!国連はそれに近いところがありますよね。世界で起こっている紛争や飢餓や経済的不平等などを解決し、世界平和を維持しようというのが目的です。グローバル化がどんどん進んで国境を越える交流や貿易が進む中で、その経済規模の拡大と成長にそれを規制したり監視したりするシステムってまだ存在しないですよね。そうしたシステムとしての役割もあります。
さてさて、なんとなく自分たちにあんまり関係なさそうなイメージですよね?日本でもそうういう活動をしている人たちがいるんですよ!政治家の方でもそういう動きに参画する方もいます。有名な機構としては世界連邦運動協会というのがあります。ニューヨークに本部があり、国連とも協同したりしています。
みなさんはこの世界政府は実現可能だと思いますか?そもそも必要だと思いますか?
こうした議論は厳密には内容は少し異なるとしても、かなり以前から存在したんですね!
みなさん13〜14世紀のイタリア人の詩人、ダンテ・アリギエーリはご存知ですか?『神曲 』がとても有名ですよね。
さて、彼も世界政府の概念について少し語っているんです。
彼はアリストテレスのように、人間はみんな共通善という共通の目的を持っていて、その達成のためには平和が不可欠であると考えます。よってその平和を実現するために世界を支配するものが必要である。それは君主や皇帝で、世界を支配する専制君主は全世界の全てを所有しているのだからそれ以上何もいらない。よって世界の平和のために行動できるはずと考えたんですね。まだ彼の時代国際政治というよりはイタリアを中心に発展していたローマ帝国、ヨーロッパ中心の考えだったとは思いますが、ここには世界を支配する何かという概念を見いだすことができますよね!
その他にもみなさんが知っているジョン・ロックやルソーといった、大きな革命に影響を与えた哲学者や政治学者たち、多くの知識人がその後に世界政府について語っています。
いろいろ小難しくなってしまうので、簡単にまとめると、賛否両論もちろん存在していました。ヨーロッパの17世紀ごろの主権国家の成立以後、国家間の覇権争いが続いた結果、何か/誰かが世界平和を守る役割をするべきだと考える賛成論は自然の流れだと思います。反対派の意見としては、戦争をするのは国家や組織であって個人ではない。よってそうした世界政府のような組織があったとしてもその平和維持能力は疑わしいというものや、そうした政府をつくったことによってもたらされる良い福利よりも、その樹立過程で犠牲となる福利の方が大きいのではないかという議論もありました。
みなさんはこういう意見についてどう思います??
許しがたいサボリン加藤です。
さぼりすぎてブログのパスワード忘れるとこでした。
趣味はワインレッドのマニキュアを塗って、手の甲の静脈の緑とのコントラストを楽しむことです。好きな味は塩味です。そんなタワゴトはおいておいて、今日はちょっと寒いですね!9月の最初の寒い風が吹くときってなんか寂しいですよね。夏が終わりみたいで。ま、夏は大嫌いなんですけどね。
ちょっとブログを休んでいる間にいろいろありましたね!911の10周年や首相が交代したり中東ではまだまだ混乱が続いていますね。アメリカではだんだん大統領選にむけて共和党の候補者たちがうるさくなってきましたね。
個人的なニュースですが最近国連でインターンを始めました。以前よりも様々な世界情勢に触れる機会が増えたので、今回はタイトルのとおり、世界政府について書こうと思います。
世界政府というとどんなイメージですかね?
全世界を支配する政府で何か恐いイメージを持つ人が多いんじゃないかな?英語だとworld governmentとかglobal governmentっていいます。世界政府じゃなくてもっと良い訳があれば教えてください。 簡単にいうと、国際社会では国の上にそれらを支配するさらに上の機関とか政府といったものは存在しないですよね?世界政府はそいいう役割を担う物で、超国家的な存在として国際問題の解決に中立的立場で関与しようという考えなんですね!国連はそれに近いところがありますよね。世界で起こっている紛争や飢餓や経済的不平等などを解決し、世界平和を維持しようというのが目的です。グローバル化がどんどん進んで国境を越える交流や貿易が進む中で、その経済規模の拡大と成長にそれを規制したり監視したりするシステムってまだ存在しないですよね。そうしたシステムとしての役割もあります。
さてさて、なんとなく自分たちにあんまり関係なさそうなイメージですよね?日本でもそうういう活動をしている人たちがいるんですよ!政治家の方でもそういう動きに参画する方もいます。有名な機構としては世界連邦運動協会というのがあります。ニューヨークに本部があり、国連とも協同したりしています。
みなさんはこの世界政府は実現可能だと思いますか?そもそも必要だと思いますか?
こうした議論は厳密には内容は少し異なるとしても、かなり以前から存在したんですね!
みなさん13〜14世紀のイタリア人の詩人、ダンテ・アリギエーリはご存知ですか?『神曲 』がとても有名ですよね。
さて、彼も世界政府の概念について少し語っているんです。
彼はアリストテレスのように、人間はみんな共通善という共通の目的を持っていて、その達成のためには平和が不可欠であると考えます。よってその平和を実現するために世界を支配するものが必要である。それは君主や皇帝で、世界を支配する専制君主は全世界の全てを所有しているのだからそれ以上何もいらない。よって世界の平和のために行動できるはずと考えたんですね。まだ彼の時代国際政治というよりはイタリアを中心に発展していたローマ帝国、ヨーロッパ中心の考えだったとは思いますが、ここには世界を支配する何かという概念を見いだすことができますよね!
その他にもみなさんが知っているジョン・ロックやルソーといった、大きな革命に影響を与えた哲学者や政治学者たち、多くの知識人がその後に世界政府について語っています。
いろいろ小難しくなってしまうので、簡単にまとめると、賛否両論もちろん存在していました。ヨーロッパの17世紀ごろの主権国家の成立以後、国家間の覇権争いが続いた結果、何か/誰かが世界平和を守る役割をするべきだと考える賛成論は自然の流れだと思います。反対派の意見としては、戦争をするのは国家や組織であって個人ではない。よってそうした世界政府のような組織があったとしてもその平和維持能力は疑わしいというものや、そうした政府をつくったことによってもたらされる良い福利よりも、その樹立過程で犠牲となる福利の方が大きいのではないかという議論もありました。
みなさんはこういう意見についてどう思います??
最近は技術革新や経済グローバル化で世界政府が再度注目されています。情報、技術、コミュニケーション、運輸の技術進歩によるグローバリズムというのはいい点だけではないですよね。以前も書きましたが国家間の相互依存の高まりや、テロや経済/金融危機、地球規模の環境問題などのリスクの全世界での共有というのは大きなデメリットですね。経済による不平等をだれが是正し、核兵器をコントロールし、資源をどう配分していくか。これらのデリケートな問題に、超国家的な組織が、どの国の利益にも偏ること無く関われれば良いなとは思います。
アインシュタインは世界政府の概念に肯定的だったんです。めちゃくちゃ簡潔にまとめて、全ての国や政府に承認された超国家的存在が法的権力をもって国家間を規制しないといけない。そして武力の行使をその機関に委ねるべきという考えでした。特に核兵器について暗示しているようにも思えますね。
最近の自由主義者の中には反対意見もあります。その大きな理由として、世界政府なるものがそんざいして中央主権的に支配するとすれば、それが行使する法やそれがもつ価値観の浸透により全世界の同質化が進む。そうすると各国家の文化や民族といった多様性や独自性が薄れるのではないかと懸念しているんですね。これについてはわたしはあまり賛成しませんね。逆にナショナリズムが覚醒されて、自国の文化や伝統を守ろうという動きが盛んになるんではないかな〜と思います。そもそも、誰も価値観をおしつけるような組織が国家の上位に存在するというのは望んでないですよね。わたしの意見では、世界政府というと何か圧迫的で恐いイメージだとは思いますが、そうではなくて例えば核兵器や武力の行使、国際紛争の司法権のみを超国家的組織に委譲して、部分的な世界政府をつくるべきではないかなと思います。国連は先にも書いたとおりそれに近いですが、やはりそれよりも国家の区切りというのは未だ強く、治外法権だとか、介入できる限界はあります。(国際刑事裁判所)ICCはみなさんご存知?ジェノサイドや紛争など国際犯罪を裁く機関ですが、条約ベースの機関で、介入できる範囲にかなり限りがあります。
こうやってみてみると、ずいぶん以前から議論されている概念ですがなかなかその実現可能性やそもそもの必要性にわからないことがたくさんありますよね。
私も正直、答えがみつかりません。
ただ、以前に国民総幸福量のところでも書いたんですが、幸福の量を量るとか、超国家的組織をつくるというのはいわばユートピア的で理想主義的でぼんやりした現実味のない議論のように見えます。でもそうしたユートピア的ものであってもそれをどう現実味を帯びたプランに具体化、具現化するかを考えるプロセス自体がとても大切だと思います。世界でたくさんの人が世界政府の意義について考えることは、世界平和や正義について考えることです。するとそうした話題に関心があつまり、今まで見えなかった問題が見えたり、もしかしたら何かいい具体案が浮かぶかもしれませんよね。
わたしがはっきりした答をまだ持っていないのでちょっとまとまりのない文章になってしまいましたが、読んでいただいてありがとうございます。
これから頑張って更新していきますので、宜しくお願いします!!
書いてほしい話題などあれば、どんどんコメントしてくださいね!!!
最後にこんな寒い雨の夜にサボリン加藤からこの一曲。